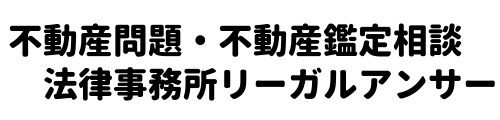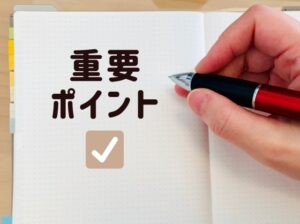建物の老朽化と立退交渉の関係
1 建物の老朽化にまつわる問題点
昭和56年以前に建築された、いわゆる「旧耐震基準」で建てられた建物、または法改正により現行基準に適合しなくなった「既存不適格建物」では、建物が老朽化しているという事情が、修繕費の負担や立退き交渉(契約期間満了による建物明渡請求)の局面で問題となり得ます。
この場合、老朽化に伴う危険性だけでなく、賃貸借契約の内容や賃料の水準、修繕費用の妥当性といった事情まで丹念に検討する必要があります。以下、関連する裁判例を概観します。
2 賃貸人の「修繕義務」はどこまで及ぶのか
京都地方裁判所平成19年9月19日判決は、老舗料亭から改装したレストランの賃借人が、賃貸の対象となっている旧耐震の建物について「新耐震基準へ補強せよ」と求めた事案です。
裁判所は、賃貸人・賃借人の双方が契約締結時に旧耐震であることを認識していたこと、旧耐震である事情が合意された賃料にも織り込まれていたこと、そして民法606条の修繕義務は「当初予定された性能」を保つ範囲に限られることなどを理由に、賃貸人の修繕義務を否定しました。
すなわち、旧耐震という事実のみで直ちに大規模補強が義務づけられるわけではなく、契約締結時の説明や賃料水準なども総合考慮して判断されます。
3 耐震不足だけで賃貸借契約は終わるのか(正当事由との関係)
東京地方裁判所平成29年11月28日判決は、築45年の喫茶店物件の賃借人が、外壁剥離と耐震不足により使用不能であるとして賃料返還を求めた事案です。
同判決は、外壁不具合には看板設置など賃借人の使用による影響も否定できないこと、外壁は修繕可能であること、旧耐震という事実のみでは「使用不能」とはいえないことを指摘し、請求を棄却しました。
ここでも、危険度のみならず、修繕の容易さや代替的利用の可否が重視されています。
4 裁判所が注目する判断要素
以上を踏まえると、裁判所は、①契約締結時の合意内容(建物の状態・賃料水準等)、②継続使用の危険度、③修繕の手間・費用といった要素から、修繕の要否や使用継続の可否を判断しています。
あわせて、補強費用と建物価値の比較、建物の明渡し交渉で提示される立退料が正当事由を補完し得る水準か、といった点も総合的に検討されています。
5 立退き交渉を有利に進めるための対応策
老朽化建物の立退き交渉(期間満了による賃貸借契約の終了)においても、賃貸人側は、耐震診断書、補強費用の見積もり、建替え後の収益シミュレーションを整え、「経済的に補強は困難であり、建替えが合理的」と説明できる体制を構築することで、正当事由を固めやすくなります。
他方、賃借人側は、利用継続の必要性や部分補強・一時移転といった代替案を技術・経済の両面から示しつつ、立退料の水準交渉に活かすのが有効です。
6 まとめ
近年の裁判例は、旧耐震や既存不適格という一点のみで修繕義務や期間満了による契約の終了を認める傾向にはなく、「契約時の説明」や「費用対効果」などの事情も踏まえて結論を導いています。
当事務所には不動産鑑定士資格を保有する弁護士が在籍し、耐震診断結果の法的評価、補強・建替えコスト試算、明渡し交渉・訴訟対応をワンストップでご提供が可能です。旧耐震ビルの活用や立退きでお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。